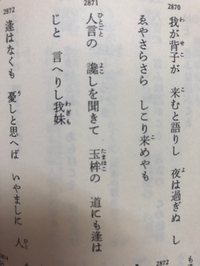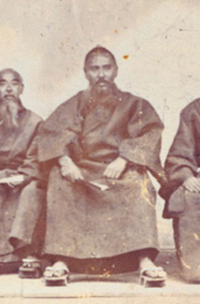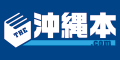2016年06月02日
セメント文化
赤瓦よりコンクリートの家が多いのね?
沖縄を初めて訪れる方によく言われます。
太平洋戦争で沖縄は戦場となり、家々が灰燼と化しました。
多くの大工も命を落としました。
壷屋から復興が始まりますが、陶器とともに赤瓦も焼かれてはいましたが、今までの家の造りだと時間やコストがかかります。
技術がさほど必要ではなく、簡単に作れる家。
台風に耐えうる家。
海に行くと、砂だけは豊富にある。…セメントならいける。
ということで、セメントブロックを大量に作りさながらレゴのように積み上げていく家に人気が集まりました。
そこから花ブロック(風通しがよく、軽い、おしゃれ)も使われるようになります。
沖縄にセメント文化は戦前からありましたが、戦後本格化します。
シーサーが、琉球石灰岩(彫刻)から、ヤチムンになると、自由な形が増えていくように、安くて自由に形成できるセメントもいろいろ応用されます。
セメント遊具。

すべり台…でも滑りません(笑)
滑らない台です。
風化して、表面がザラザラになっています。
にんじんシリシリーならぬ、人間シリシリーになります。
すべらない台は佐敷グスク近くにある広場にあります。
僕が小さい頃は、こういったセメント遊具が結構ありました。
広場は、きれいに草が刈られ、ゴミひとつ落ちていません。
誰も遊ぶことはないであろう滑らない台は、ミュージアムの展示のようでした。
これも歴史文化ですね。
沖縄を初めて訪れる方によく言われます。
太平洋戦争で沖縄は戦場となり、家々が灰燼と化しました。
多くの大工も命を落としました。
壷屋から復興が始まりますが、陶器とともに赤瓦も焼かれてはいましたが、今までの家の造りだと時間やコストがかかります。
技術がさほど必要ではなく、簡単に作れる家。
台風に耐えうる家。
海に行くと、砂だけは豊富にある。…セメントならいける。
ということで、セメントブロックを大量に作りさながらレゴのように積み上げていく家に人気が集まりました。
そこから花ブロック(風通しがよく、軽い、おしゃれ)も使われるようになります。
沖縄にセメント文化は戦前からありましたが、戦後本格化します。
シーサーが、琉球石灰岩(彫刻)から、ヤチムンになると、自由な形が増えていくように、安くて自由に形成できるセメントもいろいろ応用されます。
セメント遊具。
すべり台…でも滑りません(笑)
滑らない台です。
風化して、表面がザラザラになっています。
にんじんシリシリーならぬ、人間シリシリーになります。
すべらない台は佐敷グスク近くにある広場にあります。
僕が小さい頃は、こういったセメント遊具が結構ありました。
広場は、きれいに草が刈られ、ゴミひとつ落ちていません。
誰も遊ぶことはないであろう滑らない台は、ミュージアムの展示のようでした。
これも歴史文化ですね。
Posted by かかずひとさ at 10:06│Comments(0)
│沖縄文化